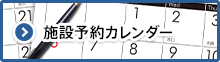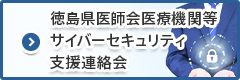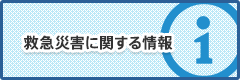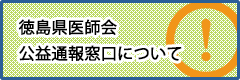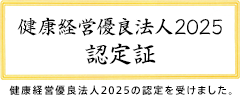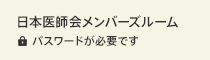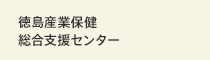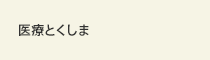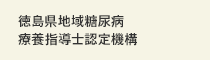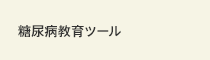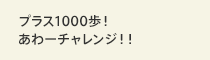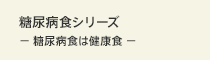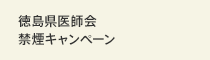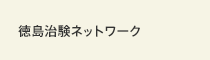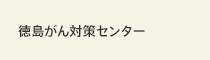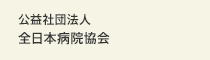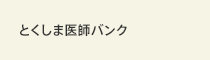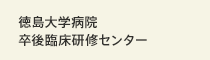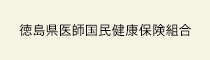- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
今月は細菌感染症に対する治療薬である抗菌剤のお話をしてきました。
抗菌剤の副作用には肝臓・腎臓・血液の障害などのあらゆる薬剤にみられる副作用のほかに、アレルギーによる発疹やショックなど抗菌剤に特有の副作用があります。さらに腸管内の常在菌を乱して発生する下痢や抗菌剤に対する耐性菌を増やすことなどが副作用としてあげられます。
発疹や下痢などは薬剤の投与を受けた個人だけの副作用ですから、多くの症状は薬剤を中止すれば症状はおさまります。しかし抗菌剤による耐性菌の増加の問題は周囲の環境に影響が及ぶので、多くの人が影響を受けます。
体力や抵抗力の落ちた乳幼児や老人、抗がん剤や免疫抑制剤の投与を受けている人たち、また事故にあった人や手術を受けた人などが耐性菌による感染症にかかると大変、治療困難な状態に陥ります。
この耐性菌の中でもっとも多く見られるのはMRSAと呼ばれる耐性ブドウ球菌です。耐性ブドウ球菌用に開発されたペニシリン(メチシリン)やセフェムにも効果のないブドウ球菌で、多くの抗菌剤に耐性を示します。
MRSAは抗菌剤を多く使用すればするほどたくさん発生しますから、それほど珍しい細菌ではありません。たとえば皮膚の化膿性病変から検出されるブドウ球菌の多くはMRSAです。夏場に多い子どもの「とびひ」は原因の大部分がブドウ球菌ですが、その多くがMRSAです。以前の「とびひ」は抗菌剤によく反応したのですが、最近はMRSAが多く、使用できる抗菌剤がほとんどありません。
日常よく出会う細菌の多くが耐性菌になっていますが、耐性菌はしばらく広い範囲の細菌に効果のある抗菌剤の使用をひかえることで減らすことができます。不必要な抗菌剤の投与を控えることで耐性菌を減らす努力が必要です。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
細菌感染症の治療に抗菌剤は欠かせないものですが、細菌感染を恐れるあまり必要のない患者さんにまで抗菌剤を使用すると耐性菌を増やす危険性が大きくなります。
細菌が抗菌剤に対して耐性を獲得する機序には、突然変異による抗菌薬耐性遺伝子を獲得する、または一部の細菌の中に薬剤に耐性を示す遺伝子を持っているものが混じっていること、などが考えられます。さらに獲得した耐性遺伝子が種類の違う細菌の間で移行することも知られています。
いずれの場合にも最初は抗菌剤に耐性のある細菌の存在する割合はそれほど多いわけではありません。しかしここに抗菌剤が投与されると、抗菌剤に感受性のある一般の細菌は抗菌剤によって大幅に減少します。その環境に残るのは抗菌剤に耐性のあるわずかの細菌です。残った耐性菌は周囲に競合する細菌が居なくなりますから、増殖しやすくなり、その環境では耐性菌が優位になります。
抗菌剤を使わなかった場合には耐性菌の割合はわずかですから、周囲の一般細菌が増殖するにつれて耐性菌は減少します。
黄色ブドウ球菌は化膿(かのう)性の病変や食中毒を起こす病原性のある細菌ですが、正常人の鼻腔や皮膚の表面にも存在します。そこに存在するだけでは病原性を示すことはありません。私たちのからだの中には病原性を示さずに存在している細菌があります。これを常在菌と言います。
私たちのからだの中には多くの常在菌が存在していて色々な仕事をしています。皮膚表面や鼻腔に常在菌が居ることによって、他の病原菌に接触しても簡単に生体内に侵入できないのです。もともと病原性を持った細菌でも、生体に有利に働く場合があるのです。
このような常在菌も抗菌剤の影響を受けますから、不必要な抗菌剤が投与されますと、生体内の常在菌を乱すことになり、病原菌が侵入しやすくなることがあります。抗菌剤を使用する場合には注意が必要なのです。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
抗菌剤の発達によって細菌感染症に対する治療は飛躍的に発展しました。その結果、乳幼児の肺炎などによる死亡率を著しく低下させることができました。抗菌剤が手軽に使用できるようになったのは社会的に安定し、経済的に豊かになったおかげです。
しかし抗菌剤が日常的に使用できるようになった反面、抗菌剤の副作用も問題になってきました。
今月は子どもの感染症の治療に欠かすことのできない抗菌剤についてお話します。
抗菌剤の開発はペニシリンに始まり、セフェムやマクロライドと呼ばれるものが小児科で多く使用されています。
セフェムはペニシリンと同じような構造を持つβ―ラクタム系の抗菌剤と言われ、ペニシリン耐性菌に有効な薬剤で、より広範囲の細菌に有効であり、ペニシリンの副作用を少なくするために開発されたものです。内服薬では服用しやすく、子どもには広く使用されています。
マクロライドは百日咳やマイコプラズマ、クラミジアなどペニシリンやセフェムでは効果がないか効果が少ない細菌に有効で、呼吸器系の感染症に多く使用されています。
抗菌剤は細菌に対して有効な薬剤ですから、小児でもっとも多いウイルス感染症には効果がありません。熱が高いからとか、のどが赤いから念のためになどと、抗菌剤を投与しても効果はありません。エンテロ、アデノ、ライノ、インフルエンザなどのウイルス感染症にも抗菌剤は必要ありません。
ロタウイルスやノロウイルスなど嘔吐(おうと)下痢症の原因ウイルスにも抗菌剤の効果はありません。嘔吐下痢症に抗菌剤を使用するとかえって下痢を長引かせることもあります。
不必要な抗菌剤療法をできるだけ少なくすることが薬剤による副作用を予防することにつながります。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
子どもの気管支喘息が増えていると言われます。その原因はわかりませんが、子どもたちを取り巻く環境が悪化しているのかもしれません。
喘息は呼吸困難を訴える病気ですから、発作が起こると普通の生活をおくることが難しくなります。喘息治療の目標は呼吸困難を取り除き、普通の生活や普通の睡眠がとれるようにすることです。学校を休むことなく、他の子どもたちと同じようにスポーツができるようにすることが治療の目標です。
喘息の病態は気管支壁の収縮による気道の狭窄(きょうさく)ですから、第一に必要な処置は狭くなった気道を広げることです。この薬が気管支拡張剤です。気管支拡張剤を吸入で使用すると、もっとも早く効果があらわれます。
しかし気管支が広がっても気管支壁にはアレルギーによる慢性炎症が残っていますから、喘息発作を反復している人は、前よりも少ない刺激で気管支が収縮するようになっています。これが気道の過敏性が亢進(こうしん)した状態です。したがってくり返す発作には気管支拡張剤を使用するだけではだんだん効果が見られなくなります。
そこで慢性の経過をとる喘息に対しては、気道の慢性炎症を抑えるために、抗炎症効果のある薬剤の投与が必要になるのです。このような治療は発作の見られない時期にも継続投与することによって、発作を予防することができます。
喘息の症状は急性期の呼吸困難の強い時期を過ぎると、少しくらい気管支の狭い状態であっても、あまり苦痛を訴えなくなることがあります。治療が不十分でも訴えが少なくなると、治療を中断してしまう危険があります。
喘息は慢性疾患ですから一時的に良くなっても治療を続ける必要があります。喘息の治療を中止するときの判断は主治医と十分相談して決めること大切です。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
喘息は子どもに多いアレルギー疾患ですが誰にでも発生するわけではありません。喘息が起こりやすいのはアレルギー体質のある子どもで、特別な環境因子に接したときに発病しやすくなります。
したがって喘息の発病を予防するためには子どもの体質を知ることや、喘息を起こしやすい環境因子を避けることが望まれます。また発病した後でも症状を悪化させるような環境因子を避けることが大切です。
アレルギー体質の多くは遺伝しますから、両親や兄弟にアトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、気管支喘息などのアレルギー疾患があると喘息発病の危険性が高くなります。
本人に食物アレルギーを原因とするアトピー性皮膚炎があるときにも注意が必要です。
多くの喘息を引き起こす原因物質は吸入アレルゲンと呼ばれるものです。このうち室内のホコリやダニ、ネコ・イヌなどペット動物の毛やフケ、室内のカビなどが吸入アレルゲンです。屋外の吸入アレルゲンはさまざまな植物の花粉や真菌類、昆虫などが挙げられます。
また喘息は呼吸器系の感染症がきっかけになって発病することが多いものです。RSウイルスやインフルエンザ、ライノウイルスなどは喘息発病のきっかけになるとともに、喘息の症状を悪化させます。さらに肺炎マイコプラズマや肺炎クラミジア、百日咳なども喘息症状を悪化させる感染症として知られています。
さらに大気汚染や室内の空気の汚れが喘息悪化につながることは言うまでもありません。とくにタバコの煙は気管支粘膜を刺激する多くの化学的な物質が含まれており、気道の過敏性を亢進(こうしん)します。アレルギー体質のある子どもの家庭では禁煙することも必要です。
アレルギー体質のある子どもにはこれらの原因物質を避けることで、喘息の発病を予防することが大切です。