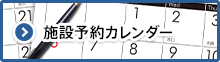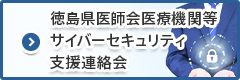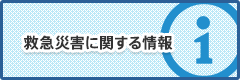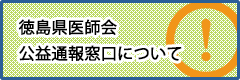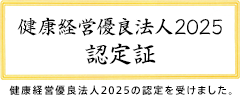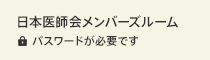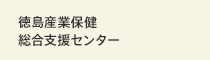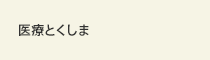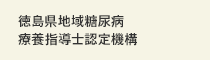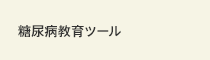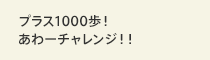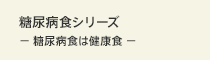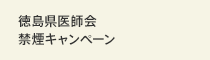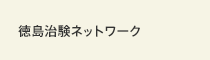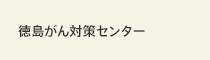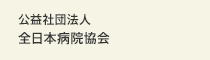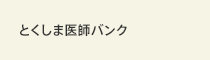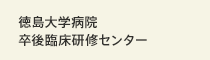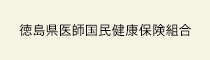- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
子どもにとって食事は大切なものです。それは、子どもが大人に比べて活動性が高く消費カロリーが多いこと、成長にともなって使用する栄養も大量に必要なためです。さらに食事は親子関係や生活習慣の確立に大きな役割を果たしているからです。今月は子どもの食事や栄養について考えてみました。
新生児期から乳児期前半は母乳または育児用ミルクだけで栄養のすべてをまかなっています。母乳が十分に飲めていれば栄養的に不足することはありません。したがって離乳食を始めるまでは母乳以外の食品を与える必要はありません。
生後5~6か月に、はじめて母乳以外の食品を口にします。これが離乳食です。離乳食にはなめらかにすりつぶした粥を使います。最初は1日1回、1さじから始め、子どもの状態を見ながら徐々に増やしていきます。食べられるようであればすりつぶした野菜なども使って、少しずつ食品の種類を増やします。
6~7か月になると離乳食の回数を2回にします。食品の固さも舌でつぶせるくらいにします。アレルギーの心配がなければ魚や肉類の他にタマゴ、豆腐、乳製品なども使用します。
9~10か月で3回食にすすめます。はぐきでつぶせるくらいの固さにして、全粥からやわらかめの米飯を使用します。この時期、母乳やミルクは欲しがるだけ与えます。
離乳食を乳児の発達段階に応じて与えるのは、子どもの「食べる」という機能が、新生児期から乳児期、幼児期にかけて徐々に発達することに合わせているためです。
食べることや飲むことは本能であり誰でも生まれつき簡単にできると思い勝ちですが、「食べる」という行動も、他の人が食べるところを見て、そのまねをして学習し、獲得する生理的な機能のひとつです。最近は、大勢で一緒に食事をとる機会が少なくなりましたから、正しく食べることを親子で学ぶ必要があるのです。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
百日咳のワクチンが開始されるまで百日咳は毎年5万人くらい発生し、2000人以上が死亡していました。1950年に百日咳の不活化ワクチンが開始されてからその発生頻度は激減して、1974年には年間200人くらいまで減少していました。
しかしその後、ワクチンによる副作用で事故が続き、接種の一時中止や接種年齢の引き上げ、ワクチンに対する不信感などのために百日咳の発生が再び増加しました。
1981年から現行のワクチンに変更され、また1994年の予防接種法改正によって接種年齢が3カ月から接種できるように引き上げられてから、再び百日咳は減少しています。
百日咳の発生は0歳児に多いのですが、最近は10歳以上や成人に多く発生しているのが特徴です。とくにワクチンを受けていない3カ月未満の乳児がかかると重症化します。またワクチン接種者や成人が百日咳にかかると典型的なせきの発作が見られないので正確な診断が遅れることがあります。
ワクチン未接種の乳幼児に特徴的なせきの発作をみれば百日咳を疑うことはそれほど難しいことではありません。しかしワクチン接種者や成人が百日咳にかかった場合の特徴は長く続く慢性のせきです。せきによる睡眠障害や呼吸困難、嘔吐(おうと)などをともなうことがあります。気管支ぜんそくなどと誤った診断を受けて治療されていることもあります。
百日咳ワクチンは大変有効なワクチンですが、接種後年月を経るとその効果は低下します。年長児や成人の百日咳は診断が難しく、ワクチン未接種者への感染源になります。長くせきの続く人は百日咳でないかを疑ってみることが必要です。
重症の百日咳や合併症はワクチン未接種者に多いとされます。また母体からの百日咳の免疫は1~2カ月で消失します。したがって定期接種である百日咳ワクチン(三種混合ワクチン)は生後3カ月を過ぎたらできるだけ早期に受けることが大切です。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
百日咳の特徴は痙咳(けいがい)と呼ばれる激しいせきです。症状の軽いカタル期に続いて発作的な激しいせきが2~3週間続くのです。このせきについてもう少し詳しくお話します。
百日咳にかかって1~2週間すると、特徴的な激しいせきの発作が見られるようになります。このせきは、息を吸い込む間もなく「コンコンコン」とたて続けにせき込みます。その後で急に息を吸い込みますからのどの奥で「ヒュー」という笛を吹くような音が聞こえます。このようなせき込みの発作を何回もくり返します。
激しいせきが起こると顔を真っ赤にしてせき込みます。首の静脈が膨れて、顔が腫れたり顔の皮下に点状出血が見られたりします。結膜の出血や鼻出血なども見られることがあります。嘔吐(おうと)をともなうことも多くなります。
激しいせきは夜間や食事中に多く見られますから睡眠障害や疲労、脱水、栄養不良などで衰弱します。
また6カ月未満の乳児が百日咳になると、呼吸の力が弱いのでせき込んだ後の息を吸い込むときの「ヒュー」という音が聞こえないことがあります。無呼吸やチアノーゼ、嘔吐などが主症状になることがあります。
さらに2カ月未満の乳児では無呼吸、肺炎、低酸素によるけいれんや脳症などの合併症が見られ、死亡することもあります。
百日咳の治療にはマクロライド系やペニシリン系抗菌薬が有効ですが、抗菌薬が有効なのはカタル期までです。激しいせきが見られる痙咳期になってからでは抗菌薬を投与しても有効ではありません。ただ百日咳菌を体内から排除するためには抗菌薬を使用します。
さらに保育所などの集団や家族内に百日咳が発生した場合には予防的な抗菌薬の投与が必要です。この場合にはワクチン接種の有無にかかわらず抗菌薬を投与します。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
激しいせきが長く続く病気の代表が百日咳です。最近では百日咳も予防接種が普及したために診察する機会は随分減りました。しかしワクチンを受けていない乳児や成人の百日咳が発生しています。今月は問題の多い百日咳についてお話します。
百日咳の原因は百日咳菌です。この細菌は飛沫(ひまつ)感染で伝染し、大変感染力の強い細菌です。百日咳菌はさまざまな毒素を持っていて、この毒素によって百日咳特有の症状がひき起こされます。また母体からの免疫が1~2月で消失するために乳児期早期でも百日咳にかかることがあります。
百日咳の潜伏期間は7日から10日です。百日咳菌が気道に侵入して感染が成立すると、細菌本体から数種類の百日咳の毒素が産生されて放出されます。これらの毒素によって百日咳特有のせきがあらわれます。
百日咳はその発現時期によってカタル期、痙咳(けいがい)期、回復期の3つに分けられます。
カタル期に見られる症状は鼻みず、くしゃみ、せき、涙、結膜充血など普通のかぜ症状と差はありません。熱はほとんど出ません。この時期は1~2週間です。症状が軽いためにほとんどが上気道炎(かぜ)として見過ごされています。家族内に百日咳の患者さんがいるなど、百日咳を疑う状況がなければ正しい診断をつけるのは難しい時期です。
痙咳期には百日咳特有の激しいせきが見られます。この時期は2~3週間続きます。激しいせきは夜間や食事中に強くなるために睡眠障害や栄養障害を起こします。さらに乳児期早期には激しいせきよりも無呼吸やチアノーゼが見られることがあります。
回復期は百日咳菌が消失して気管支粘膜が修復される時期です。特有のせきは減少しますが時々見られます。
百日咳は症状が1カ月以上続きます。乳児がかかると大変ですから予防が大切な病気です。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
子どもの発熱原因の中でもっとも多いものは呼吸器系の感染症ですが、その大部分はウィルス感染症です。したがって発熱の子どもを診た時に抗菌剤と解熱剤を投与していたのは理由の無い過去の治療となりました。
発熱は感染症に対する免疫能を誘導する大切な症状のひとつです。発熱初期に熱だけを下げる処置は適切な処置とは言えません。
しかし発熱は頭痛や倦怠(けんたい)感をともない食欲低下や睡眠障害など、子どもの体力を消耗させることもあり、どうしても苦痛が激しい場合に解熱剤の投与を考えます。
現在使用されている解熱剤はほとんどがアセトアミノフェン(商品名:アルピニー、アンヒバ、カロナール)です。坐剤や内服薬として使用します。多くの市販の総合感冒薬にも入っています。アセトアミノフェンは使用できる解熱剤の中ではもっとも安全な薬です。過量に投与すれば肝機能障害を起こすことがありますが、適切な投与量を守ればほとんど副作用はありません。
日本での使用はそれほど多くありませんが、イブプロフェン(ブルフェン、ユニプロン)も解熱剤として使用可能な薬剤です。アセトアミノフェンよりも解熱効果、鎮痛効果ともにすぐれていると言われます。
以前はメフェナム酸(ポンタール)やジクロフェナクナトリウム(ボルタレン)も子どもの解熱剤として使用されてきましたが、これらの薬剤はインフルエンザ脳症を引き起こす可能性の高い薬剤と考えられ現在では子どもの解熱剤として使用されることはありません。
大人の薬剤を誤って子どもに投与することのないように注意する必要があります。
最後に解熱剤の使用法ですが、発熱初期に悪寒があり寒気を訴えている時期には解熱剤を使用しても熱は下がりません。最初の1~2日熱を出し切ってから解熱剤を使用すると、効果がいいと言われます。