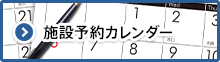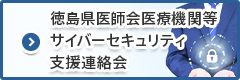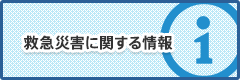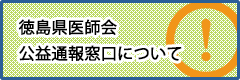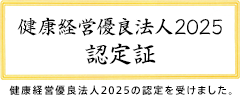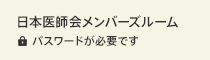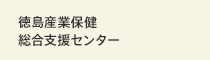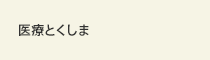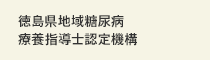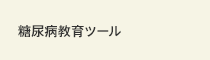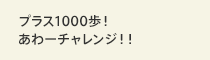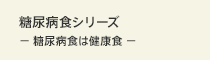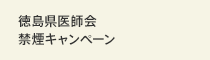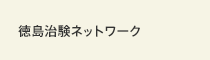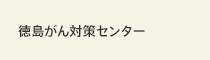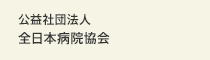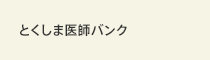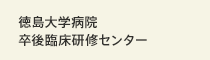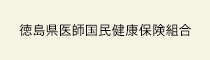- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
ポリオ(急性灰白髄炎)は小児麻痺を来すウイルス性疾患です。今では定期予防接種として乳児期にワクチンを投与されていますからポリオ患者を見ることはありません。今月は現在、日本でほとんど撲滅されたポリオの問題点について考えてみました。
ポリオは1960年(昭和35年)に全国で大流行して年間5000人以上の患者が発生しました。当時、ポリオワクチンは認可されていませんでしたので、1961年にカナダおよび旧ソ連からワクチンを緊急輸入し、全国1300万人の小児に一斉投与し、同年より急速に患者数の減少をみました。この時にポリオワクチンの効果が証明されたのです。
現在では日本を含む東アジア、オセアニア地域、南北アメリカ大陸、ヨーロッパの各地域ではポリオは制圧されています。インドとその周辺諸国、西アフリカのナイジェリアを中心とした地域の2大流行地ではまだポリオが制圧されていません。したがってこれらの地域や国への海外渡航者などが国内に持ち込む恐れが残っています。
ポリオは夏かぜの代表であるヘルパンギーナや手足口病の原因と同じエンテロウイルスに属します。のどに入ったウイルスはのどや小腸粘膜の細胞で増殖します。その後、ウイルスは糞便中に排せつされますが、一部はリンパ節から血液中に入り脊髄をはじめ中枢神経に侵入します。脊髄の前角細胞や延髄の運動神経細胞に感染するとこれらの細胞障害のために運動麻痺や呼吸障害などの症状が出現します。
ポリオウイルスに感染しても大部分は不顕性感染に終わります。発熱や軽い胃腸症状のみで終わるものが約4%、無菌性髄膜炎が0.5~1%、麻痺を示すものが約0.1%と言われます。感染から発病までの潜伏期間はおよそ1~2週間、発病から糞便中にウイルスが排出される期間は約1カ月とされます。ポリオウイルスに効果のある薬剤はありません。したがってポリオはワクチンで予防すべき病気なのです。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
突発性発疹症(突発疹)がヒトヘルペスウイルス6型(HHV-6)で起こることが明らかにされたのは比較的最近です。エイズの原因ウイルスを検索中に発見されたウイルスの中にHHV-6が含まれていたのです。その後発見されたヒトヘルペスウイルス7型(HHV-7)でも突発疹を発病することがわかりました。
突発疹の主な症状は高熱です。発病初期の所見の少ないときには他の発熱性疾患との鑑別が問題になります。とくに細菌感染を見逃すようなことがあっては大変です。高熱だけで所見がないときには血液検査で白血球数を測定し、その異常の有無で細菌感染と鑑別しておくことも必要です。ウイルス疾患である突発疹には抗生剤は無効ですから、細菌感染が否定できれば抗生剤の投与は控えるべきでしょう。
突発疹の合併症として多いものが熱性けいれんです。突発疹による熱性けいれんは他の熱性疾患による熱性けいれんよりも頻度が高いと言われます。またけいれんが長く続く重積状態になることがあることや熱性けいれんを反復する傾向のある場合があることなども指摘されています。
このことはHHV-6がマクロファージという免疫に関与する白血球に感染して脳に侵入しやすいことや、脳にあるグリア細胞などに潜伏感染する性質があることと関係しているのかも知れません。
突発疹による熱性けいれんの問題点は、初発であること、重積状態になることがある、反復する場合などです。初発の熱性けいれんでは単純性熱性けいれんとして短時間で止まるかどうかが大切です。1回目の熱性けいれん時に将来反復するかどうかを予測することは難しく対応に苦慮します。重積状態の場合には脳炎・脳症なども考慮すると同時にできるだけ早くけいれんを停止させる必要があります。
突発疹の原因ウイルスであるHHV-6は神経系に潜伏することから多くの神経疾患の発生原因になることが推測されています。ありふれた熱性疾患ですが今後の研究の結果からは明らかにされることがまだまだありそうです。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
突発性発疹症(突発疹)は乳児の熱性疾患でほとんどの乳児が2歳までにかかるとされます。しかし、かかった子どもが全員、典型的な突発疹を発病する訳ではありません。発熱だけや発疹だけの場合もあり、また発病せずに終わる場合もあると言われます。時には突発疹に2度かかることがあります。
突発疹をウイルス学的にはっきり説明できるようになったのはごく最近です。突発疹の原因ウイルスはヒトヘルペスウイルス6型(HHV-6)とされます。このウイルスは1980年代にエイズの研究中に発見されたもので、1988年に日本人によって突発疹の原因であることが明らかにされました。その後、突発疹と同じような症状がヒトヘルペスウイルス7型(HHV-7)でも見られることが明らかになりました。
HHV-6に比べるとHHV-7による突発疹は年齢的に遅れてかかること、さらに症状が軽くすむことも知られています。
突発疹の伝染経路については確定的ではありません。発熱中の乳児の唾液からウイルスが分泌されると言われますが、突発疹の原因ウイルスは成人の体内に潜伏したウイルスが、母体免疫が低下した乳児に侵入して発病すると考えられています。そして発疹が出現する時にはウイルスの排出はなくなります。したがって乳幼児の間で感染して流行することはなく、感染予防のために解熱した後いつまでも隔離しておく必要はありません。また、突発疹の発生に季節性はなく、1年中同じような頻度で発生します。
突発疹に対する特別な治療法はありません。発熱はウイルスを排除するための免疫反応と考えられますから、一般に解熱剤の使用には慎重でなければなりません。
最初の高熱で突発疹を疑っても発疹が出るまで確定診断に至らないことで不安が増します。他の熱性疾患を除外しながら乳児の全身状態を把握し経過観察していくことが大切です。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
突発性発疹(ほっしん)症(突発疹)は乳児の発熱性疾患でめずらしいものではありません。生後はじめて出す熱の原因としてよく知られていますが、この疾患の原因がヘルペスウイルスの仲間であるということが明らかにされたのはそれほど古いことではありません。今月は突発疹について考えてみたいと思います。
突発疹は乳児の母体免疫が減少する時期に発病する疾患です。したがって生後6カ月から1歳に発病のピークが見られ、わが国では2歳までにほとんどの乳児が感染を受けるとされます。
主な症状は突然の高熱であり、軟便をともなう以外にはほとんど他の症状は見られません。高熱の割には比較的機嫌もよく、全身状態もそれほど悪化することはありません。高熱は約3日間持続すると自然に下がります。解熱とともに皮膚に発疹が出現して突発疹の診断がつきます。発疹は薄い紅斑で、体幹部を中心に出現し四肢や顔面にも広がることがありますが、3日くらいで消退します。
突発疹は多くの場合に高熱と発疹だけで終わりますが、時に熱性けいれんをともなうことがあります。熱性けいれんの頻度は他の熱性疾患に比べて高率に発生すると言われます。また高熱のある時期に大泉門がふくれて神経系の合併症を疑われることもあります。
突発疹は、生後初めて経験する発熱の原因となることが多く両親は大変不安になります。小児の救急疾患としても重要な疾患です。
突発疹は自然に経過を見れば、3日間くらいで解熱し、自然に原因が明らかになり治癒する疾患ですから特別な治療は必要ありません。安静と水分や栄養補給をして経過を観察していればいいのです。
突発疹の多くが急な発熱で発病し、それも初めての発熱である場合が多く、救急現場での初期対応が問題になります。この疾患を疑った場合には他の熱性疾患との鑑別をするとともに、いかに両親の発熱に対する不安を解消するかがポイントになります。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
おたふくかぜの予防にはワクチンが唯(ただ)ひとつの方法です。今回はおたふくかぜワクチンの重要性についてお話します。
ワクチンの役割には2種類あります。ひとつは個人の免疫を高めてその病気にかからないようにすることです。もうひとつは集団でワクチン接種を行い、集団の免疫を高めることで、その病気を社会からなくしてしまおうとするものです。
現在、おたふくかぜワクチンは任意接種ですから個人の免疫に対しては自分で費用を負担するほかありません。国の法律で定められた定期接種と言われるワクチンは集団の免疫を高めるという考え方に基づいて行われていますが、日本ではおたふくかぜワクチンを定期接種にして日本からおたふくかぜをなくそうとは考えていません。
おたふくかぜの予防接種を定期接種にしている国ではおたふくかぜの発生をほぼ100%抑制することに成功しています。日本では1989年にMMR(麻疹・風疹・おたふくかぜ3種混合ワクチン)としておたふくかぜワクチンが定期接種に含まれた時期があります。しかしワクチンによる髄膜炎の発生が多く1993年にMMRは中止になりました。MMRが導入されていた時期にはおたふくかぜの流行が抑制されていましたが、MMR中止後再び流行が見られています。副反応で予防接種が一度中止になると国民はワクチンに対して不信感を抱くようになり、ワクチンを再開することは大変困難なことになっています。
世界中では多くの国で、おたふくかぜワクチンはおたふくかぜ単独またはMMRとして2回接種を定期接種として行っています。日本ではおたふくかぜワクチンを危険なものとする考え方から抜け出すには至っていません。
おたふくかぜはもともと神経に親和性が高く髄膜炎を起こしやすいウイルスです。したがってワクチンで髄膜炎の起こる確立をゼロにすることはできません。しかしワクチンで髄膜炎が起こる確率は、自然のおたふくかぜによる髄膜炎の頻度とは比べものにならないくらい低いものです。できるだけ早くワクチンを定期接種にして、日本からおたふくかぜの流行をなくしたいものです。