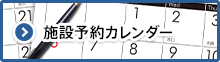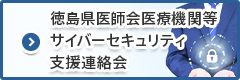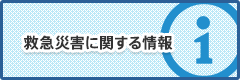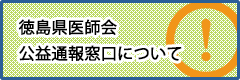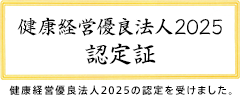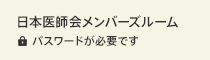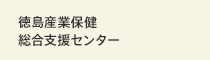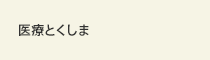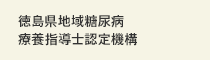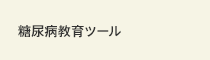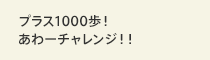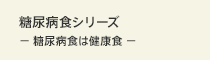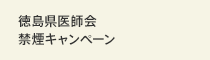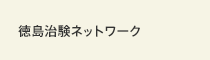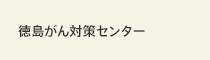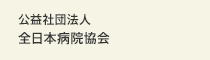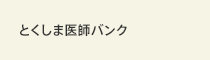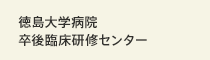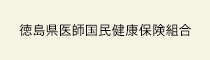- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
熱性けいれんは健康な子どもに見られ、大部分が自然に治ってしまう疾患ですが、中には熱性けいれんから将来てんかんを発病する人や二次的な脳障害を来す人もあり注意が必要です。自然に治ってしまう単純性熱性けいれんは、発作の持続時間も短く、発作型も左右対称性で、ほとんどが1~2回のみの発作で5歳くらいまでには治ってしまいます。発作が何回も反復するもの、長時間持続するもの、同じ日に繰り返すもの、けいれん発作の左右差が著しいものなどは複雑性熱性けいれんと呼ばれ治療や検査が必要な熱性けいれんとして区別されます。
熱性けいれんが初めて起こった時には、てんかん発作と同じような症状で、両者を区別することは出来ません。しかし脳性麻痺や発達遅滞など脳に障害を持つと考えられる子どもが熱性けいれんを起こした場合には、てんかんが発熱をきっかけに発病した可能性をまず第一に考えておかなければなりません。また熱性けいれんで問題になるのは、けいれんの持続時間が長いものや、4時間以内にけいれんが反復して起こる場合で発作が重積する時にはけいれんの原因検索はもちろん、早期にけいれんを止めることが大切です。
一般に熱性けいれんは数分で自然に止まりますが、15分以上も続く時には速やかに止める必要があります。長いけいれんには脳炎・脳症、血糖や電解質異常などの代謝異常が原因として隠れていることがありますし、長いけいれんの後には低酸素症から脳障害を起こすこともあります。けいれん発作が片側に優位で左右差が著明な場合には、脳の血管障害や外傷、腫瘍などの異常がある場合もあり脳波以外のCTやMRIなど画像診断が必要となります。これらの長いけいれんや反復する発作を経験した時には精密検査と共に早期に完全にけいれんを止めることが、二次的な脳障害を予防する上で大切なことです。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
子どもは大人に比べてひきつけを起こしやすいとされ、特に高熱にともなう熱性けいれんをよく経験します。子どもが急に意識がなくなってひきつけ始めると、呼吸が止まり、顔色が蒼くなり、口唇がチアノーゼとなり嘔吐を伴うことなどが多く、患者さんが外来で発作を起こした時など、何度見ても自然に止まるのかどうか不安になることがあります。家族にとっても、このまま死んでしまうのではないかと思うことさえあるのではないでしょうか。
けいれんは神経疾患の代表的な症状の1つですから、けいれんを見た時にはまず神経疾患を考えることになります。しかし熱性けいれんの多くは、神経疾患や発達障害がなく元気な子どもに起こり、ほとんどの子どもでは大きくなると自然に治ってしまいます。今回は子どもに多い熱性けいれんについてお話ししたいと思います。
日本においては熱性けいれんは小児人口の7~8%に発生するとされていますが、髄膜炎や脳炎など中枢神経感染症によるけいれんは熱性けいれんから除外します。熱性けいれんの初回の発作は生後6カ月から3歳くらいに起こり、ほとんどの人が1~2回の発作だけで自然に治ります。しかし中には発作を繰り返す人があり、発熱の度に発作を起こす人には予防が必要となります。2回目の発作を示す人が約30%、3回以上繰り返す人が約9%あるとされます。熱性けいれんは1歳未満で発生した場合など低年齢であるほど再発しやすいと言われます。また熱性けいれんは遺伝しやすいとされ、父母など一親等内にあれば再発率は50%であるとされます。再発の時期については、6カ月以内に50%、1年以内に75%、2年以内に90%の人が再発するとされます。つまり2年間、熱性けいれんが再発しなければ、90%以上の人は治ったと考えて良いことになります。いたずらに不安がらずに、どのようなタイプの熱性けいれんであるのか、十分に見極めておきたいものです。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
原因不明の乳幼児突然死症候群(SIDS)について、従来は東洋人よりも欧米人に多い疾患とされていました。これはその後の調査で人種による遺伝的な要因よりも、育児環境が最も大きく関与していることが明らかにされました。特にアメリカでは子どもを乳児期から一人で夫婦と別の部屋に寝かせることや、うつ伏せに寝かせる習慣があります。これらの習慣がSIDS発生の危険性を増大させていたのだと考えられます。
平成10年に旧厚生省はSIDS発生の危険因子として、うつ伏せ寝は仰向け寝の3倍、人工栄養法は母乳栄養法の約5倍、両親の習慣性喫煙は非喫煙の約5倍、発生頻度が高いことを示しました。うつ伏せ寝とSIDSの関連については顔が見えにくい、柔らかい寝具で鼻が圧迫されることなどが考えられていますが、仰向け寝よりうつ伏せの方がよく眠る傾向があり覚醒反応が起こり難いのではないかと考えられています。母乳栄養児については、感染症に対する抵抗力の違いや、口腔の発達が異なることが考えられています。タバコについては、妊娠中の直接・間接の喫煙によりなんらかの有害物質が児の呼吸中枢に作用している可能性が考えられています。
その他、育児環境として従来の日本のように添い寝や親子で川の字に寝る場合には、常に子どもは親の傍で寝ており、子ども部屋で子ども一人寝かせる場合よりもSIDS発生の頻度は低くなります。
SIDSで子どもを失った母親は子どもの突然の死に精神的なショックを受けるとともに自分の過失ではないかとの自責の念に駆られることが多く、さらにSIDSが周囲に十分理解されていないために非難の目で見られることがあります。この上に警察や医療従事者から様々な質問を受けることとなります。SIDSという正確な診断を下すためには解剖することも必要となります。このような母親に対する精神的なサポートが必要なことは言うまでもありません。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
乳幼児突然死症候群(SIDS)の原因は、生前の病歴や死後の剖検によっても原因が明らかにされない疾患とされます。今まで元気だった乳児が突然死亡して家族や社会に与える影響は非常に大きいものです。家庭だけでなく保育園や託児所で突然死が発生すると責任問題に発展することもあります。
突然死は睡眠中に発生するために早朝に発見されることが多いとされますが、昼寝の時にも発生します。SIDSの原因は明らかではありませんが、その発生には睡眠中の無呼吸が関係していると考えられています。健康な乳児でも睡眠時に無呼吸が見られることは珍しくありません。睡眠中には呼吸だけでなく血圧・脈拍・体温などが様々に変動しており、特に浅い睡眠やレム睡眠の時には変動が大きく、不規則な呼吸から無呼吸になることがあります。また乳児期早期には深い睡眠が少なくレム睡眠や浅い睡眠の割合が多く、さらに明け方にはレム睡眠が増加し、それだけ無呼吸の出現も多くなります。
しかし、ほとんどの乳児が無呼吸から自然に回復するのに、SIDSを起こした児はなぜ回復しなかったのでしょうか。これまでに多くの調査研究がなされてきた結果、睡眠中の無呼吸からの回復が遅れるという、覚醒反応の異常がその原因であると考えられます。睡眠中に無呼吸になると、血中の酸素濃度の低下、二酸化炭素濃度の上昇に伴って、呼吸中枢が刺激され覚醒反応が起こって呼吸が再開するとされていますが、ここでなんらかの異常で覚醒反応が起こらなければ無呼吸からの回復が遅れて、さらに重篤な低酸素症となり、回復不能の状態に陥り死に至ると考えられます。
覚醒反応の異常の背景には、呼吸中枢の未熟性や慢性的な低酸素環境に置かれることで覚醒反応が悪くなるなどと考えられています。しかし、SIDSは特別な子どもにだけ起こる特殊な病態ではなく、誰にでも起こる可能性を持った疾患であるとされるので注意が必要です。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
健康だと思われていた乳児が睡眠中に突然、呼吸を停止して死んでしまう病気、乳幼児突然死症候群SIDSが最近問題になっています。この疾患の原因は死亡前の病状や死後の解剖によっても明らかにすることは出来ません。我が国では乳幼児の死亡原因の第3位にあげられ、全体に乳児死亡が減少している中にあってその発生頻度は、乳児2,000人に1人、1年間に約600人の乳児がSIDSで亡くなっていると考えられています。
SIDSが問題になるのは原因不明の突然死で、死亡直前の病状や死後の解剖によってもその死亡原因が明らかにされないことです。剖検してみると、生前に気がつかれていなかった心疾患や神経疾患、髄膜炎や肺炎などの感染症、誤嚥による窒息や転落事故による頭蓋内出血、薬物中毒などの他、虐待や犯罪などによる死亡原因が明らかになることがあります。このような死亡原因が見つからない場合にSIDSとされます。剖検をすることで事故や犯罪による死亡を鑑別することはきわめて大切なことです。我が国の乳児の突然死に対する剖検率は20%以下と低いものです。はっきりした原因が明らかにされたものはSIDSから除外しなければなりません。昔は母親の不注意による事故や窒息死と診断された症例の中にこの疾患が隠れていたものと思われます。また臨床的に原因不明の突然死を遂げた乳児を剖検することなくSIDSと診断することがありますが、虐待や事故による症例が含まれている可能性は否定できません。
SIDSは生後4ヵ月に発生のピークがあり、生後6ヵ月までにその80%が発生します。SIDSは健康な乳児に発生するもので予防が難しい疾患とされています。しかし最近は育児環境を整備することでその発生を低くすることが出来ることも明らかにされています。SIDSは珍しいものではなく、身近な疾患として十分に注意したいものです。