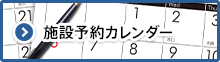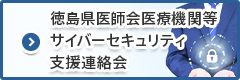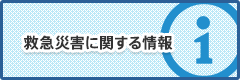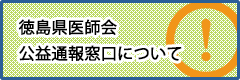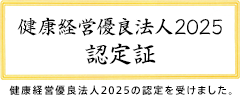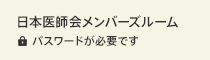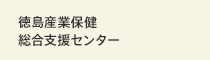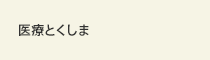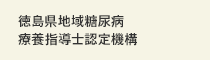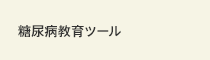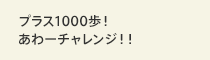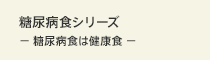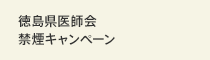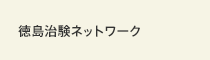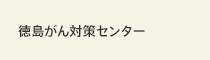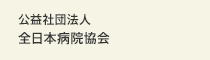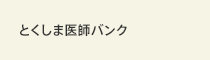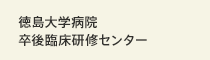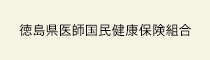- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
ひうら小児科 日浦 恭一
インフルエンザ菌b型ヒブによる全身感染症、とくに髄膜炎はとても恐ろしい病気です。日本でヒブ髄膜炎にかかる子どもの数は毎年500~600人程度です。元々欧米に比べて日本ではヒブ髄膜炎は少ないと言われていましたが、最近の調査では日本のヒブ髄膜炎も欧米のヒブワクチン導入前と同じくらいの頻度であることが明らかにされています。
欧米では1990年頃からヒブワクチンが定期接種として導入されてからヒブ髄膜炎はほとんど見られなくなっています。
日本では以前にはヒブ髄膜炎の頻度は低いと考えられていて、ヒブワクチンの重要性がそれ程認識されていませんでした。そこでヒブに対しては個別に抗菌薬を投与することで対応してきました。しかし重症細菌感染症を恐れるあまり抗菌剤を使用しすぎた結果、ヒブに対する抗菌薬の耐性化が進み内服薬ではほとんど効果のある薬剤がなくなりました。
日本でも欧米に遅れること15年、やっとヒブワクチンの重要性に気づいたのです。昨年12月にヒブワクチンが日本でも発売され使用できるようになりました。
ヒブワクチンの接種法は現行の3種混合ワクチンの接種法と同じです。生後2ヶ月から7ヶ月の間に開始し、4~8週間ごとに3回接種し、1年後に1回追加接種を行います。生後7ヶ月を過ぎて開始するときには2回接種になります。生後1年以上5歳未満で接種する場合は1回だけです。
ヒブワクチンの副作用は局所の発赤や腫れだけでDPTとほとんど同じと言われます。
ヒブワクチンは任意接種であるため、費用は全額自己負担となります。ヒブ髄膜炎にかかると入院の治療費がかかるだけでなく、後遺症が発生すればその治療費や療養にかかる費用を一生負担しなければなりません。
早期にヒブワクチンを定期接種にして、すべての子どもたちが平等に、無料でヒブ髄膜炎から守られる社会にしたいものです。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
ひうら小児科 日浦 恭一
インフルエンザ菌b型(ヒブ)は乳幼児の重症感染症の原因菌として重要な細菌です。とくに全身感染症の中でもヒブによる髄膜炎はもっとも注意すべき感染症です。
乳児の髄膜炎の原因菌の中でヒブはもっとも頻度の高いもので、全国調査によると小児人口10万人あたり8.5人程度の発生率と言われます。ヒブによる髄膜炎はほとんどが5歳未満ですから、日本では毎年500人から600人の子どもがヒブによる髄膜炎にかかっている計算になります。
髄膜炎の症状には特別な症状があるわけではありません。初発症状は発熱、頭痛、嘔吐、不機嫌、けいれんなど一見普通のかぜを思わせる症状と異なるところはありません。髄膜炎はこのような症状や簡単な血液検査だけで正確な診断はつきにくいものです。
上気道に定着したヒブが血液中に侵入して菌血症を起こすとヒブが全身に散布されて髄膜炎などの全身感染症を起こします。
菌血症の症状は発熱または低体温、不活発、傾眠、不機嫌や哺乳不良、発汗、嘔吐、易刺激性などがありますが、特別他の感冒と区別できるような症状はありません。
髄膜炎の症状は感冒症状に続く発熱、嘔吐、易刺激性からけいれん、意識障害へ進行します。項部硬直などの髄膜刺激症状と呼ばれる髄膜炎特有の症状は見られないこともあります。
髄膜炎の診断の確定のためには髄液検査が必要です。髄液からヒブを検出することが正確な診断につながります。
ヒブ髄膜炎の治療には適切な抗菌剤の投与が必要です。ヒブ髄膜炎の治療が難しいのは、抗菌剤の髄液内への移行が悪く大量の抗菌剤が必要なこと、ヒブは抗菌剤に耐性を示すために、使用可能な抗菌剤が限られる点にあります。
治療効果が悪ければ患者さんは亡くなるか後遺症を残します。ヒブ髄膜炎にかかった子どもの約5%が死亡、約25%に後遺症が残るとされます。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
ひうら小児科 日浦 恭一
最近、ヒブワクチンという言葉を新聞やテレビで目にすることが多くなりました。今月はこれまであまりなじみのないヒブおよびヒブワクチンについて考えてみました。
ヒブとはヘモフィルス・インフルエンザ(インフルエンザ菌b型)つまりHibのことです。インフルエンザ菌は血清型によってaからfまでに分類されます。この中でb型菌(ヒブ)が臨床的にもっとも問題になるのです。
インフルエンザ菌と言うと冬に流行するインフルエンザとまぎらわしいのですが、それはこの菌が1892年にインフルエンザの流行時にインフルエンザ患者の喀痰や肺組織から発見されたためです。その後1933年にインフルエンザウィルスが発見されて、ウィルスによるインフルエンザ感染症とヒブは無関係であることが明らかになりました。
ヒブは人にのみ感染する細菌で、人の鼻やのどで保菌されます。保菌者は人口の1~5%いるとされますが、保育施設などの小児の保菌者は25%に上ると考えられています。ヒブは唾液を介して飛沫または直接接触して人から人に伝播します。
ヒブは病原性が強く、髄膜炎や肺炎、敗血症、喉頭蓋炎など全身の重症感染症を起こすことが知られています。ヒブが感染して発病するのはほとんどが5歳未満の乳幼児です。乳幼児の重症感染症の原因細菌としてヒブはとても重要なものです。
ヒブに対する免疫は5歳以上の多くの子どもは獲得しています。これに対して、0歳児ではほとんどの児が免疫を持っていません。
0歳児の細菌感染症は診断が非常につきにくいものです。とくに乳児期早期の感染症では典型的な症状が現れにくく、診断がむずかしいものです。さらにヒブは抗菌剤に対して耐性を示すことが多く、ほとんどの内服抗菌剤では効果が見られません。
診断がつき難く、治療が難しいヒブに対しては乳児期早期からの予防が大切なのです。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
ひうら小児科 日浦 恭一
タバコの煙に含まれる物質の中で大切なのはニコチンです。ニコチンはタバコの主成分でタバコに依存性の生ずる原因物質です。
ニコチンの吸収は非常に速く、喫煙して煙の中のニコチンが肺に入り、毛細血管から吸収されて全身に運ばれ、7秒で脳に到達します。ニコチンは脳内のニコチン受容体と結合し、脳から抗不安作用のあるセロトニン、幸せな気分にさせるドーパミン、血管収縮と血圧上昇や興奮作用のあるアドレナリンを生じさせることが知られています。
タバコを止められなくなるのはセロトニンやドーパミンの作用によるものです。喫煙者は常に体内のニコチン濃度を一定に保とうとして喫煙をくり返すのです。
子どもに禁煙教育が大切な理由にはいくつかあります。まず初めて喫煙するのが小学生か中学生であること、喫煙年齢が低いほど習慣性や依存性を獲得しやすいこと、喫煙開始年齢が低いほど禁煙が行い難いこと、喫煙期間が長いほど呼吸器障害が大きくなること、母親の喫煙は影響が大きく、その喫煙率はこの数年減少していないことなどです。そのために小児期からの禁煙教育はとても大切なのです。
海外では多くの国の政府が喫煙の害を積極的に国民に知らせ、タバコに高額の税金をかけて価格を上げることで国民の喫煙率を低下させる政策を実施しています。
しかし日本ではタバコの有害性を国民に知らせず、価格も低く抑えてタバコの売り上げを増やして、タバコからの税収を重視する政策をとっています。
未成年者の喫煙は法律で禁止されています。これは喫煙者を罰するための法律ではなく、未成年者のからだを守るための法律です。未成年者よりもさらに弱い存在である胎児と乳幼児の受動喫煙を防ぐためにはさらに喫煙率の低下を目指す方策がとられる必要があるのです。
- 詳細
- カテゴリー: 小児科相談
ひうら小児科 日浦 恭一
タバコによる健康被害の中で問題になるのは女性の喫煙です。とくに妊婦の喫煙の問題点は女性自身の身体に有害であること、妊娠合併症の危険性が増加すること、胎盤を通ったタバコの煙が胎児にも影響することです。受動喫煙でも同じような影響を受けます。
女性の喫煙の恐ろしさは、妊娠に気づくまで喫煙を続けると、胎児の重要な器官が形成される妊娠初期にタバコの有害物質が作用して、胎児に奇形が生じる危険性がある点です。この危険性は家庭や職場における受動喫煙でも同様です。
喫煙妊婦の妊娠合併症としては不妊症、子宮外妊娠、自然流産などの頻度が高くなり、胎盤の異常として前置胎盤や胎盤早期剥離など、また早産や死産、新生児死亡の危険性も高くなると言われます。
タバコは胎児の成長にも影響します。これはニコチンによって胎盤や臍帯、胎児への血流量が減少すること、一酸化炭素によって酸素欠乏状態になること、シアン化合物によって蛋白合成が阻害されることなどが影響すると言われます。このように妊婦の喫煙は胎児の子宮内発育遅延の原因となり、出生後にも身体発育に悪影響をおよぼすと言われます。
タバコの煙が影響する胎児の奇形には水頭症や小頭症、四肢欠損や湾曲、二分脊椎、先天性心疾患、尿路奇形、口唇口蓋裂などの可能性があるとされます。
妊婦の喫煙は出生後の子どもの疾患発生にも影響することがあると言われます。呼吸中枢が影響を受けると睡眠時無呼吸や乳幼児突然死症候群を起こす可能性高くなります。
また中枢神経系が影響を受けると、知的発達の遅れ、注意欠陥・多動性障害など軽度発達障害、問題行動を起こす子どもたちが生まれる可能性が高くなると言われます。
妊娠中の女性の喫煙だけでなく、妊娠の可能性のある女性のそばで喫煙することも妊娠や胎児、子供の発達にも大きな影響をおよぼす可能性があるのです。